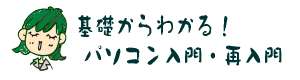どこまでがOSの範疇か
- 著者:YAMANJO
- 公開日:2008年7月9日
- 最終更新日:2024年10月31日
OSが提供する機能や役割は多岐に及びます。そのため、どこまでがOSの機能の範疇なのかが曖昧になっています。こうした問題もあることを理解しておきましょう。
どこまでがOSの機能や役割の範疇か?
これまでOSの役割について学習してきましたが、その役割は多岐に及び、どれもが重要です。
基本的にはアプリケーションソフトの基盤となる機能を提供することが主な役割です。しかし、技術が進化するにつれて、OSも進化を続けています。
Windows95発売当時と現在の最新OSであるWindows11とでは、実装されている機能やGUIに大きな差があり、進化にともなってOSの機能も増えています。
特にインターネットに関連する技術の進歩は凄まじく、ひと昔前では文字だけだったウェブサイトが、動画配信、大容量データの送受信、ショッピング、決済、クラウドサービスなどが可能になり、日常生活になくてはならないインフラに成長しました。
こうしたサービスの拡大にともなってOSも対応を重ね、様々な機能を実装していきます。ある意味、当然のことです。
しかし、基本ソフトウェアとして他のアプリケーションソフトに大きな影響力を持つOSが機能を増やすということは、すでにある他のアプリケーションソフトにも大きな影響を与えることになります。
大きな問題となったのは、「Internet Explorer(インターネット エクスプローラ)」 と呼ばれるブラウザがOSに実装されたことです。(ブラウザについては、インターネットの仕組み の章で詳しく学習します)
Internet Explorer(IE)は、ウェブブラウザと呼ばれるインターネット上のウェブサイトを閲覧するためのアプリケーションソフトです。このサイトをご覧になっているということはブラウザを利用しているということですが、ブラウザは何を利用されているでしょうか?
現在のWindowsの標準ブラウザ「Microsoft Edge(エッジ)」はIEの後継ブラウザになっています。ブラウザにはこのほか「FireFox(ファイアフォックス)」、「Safari(サファリ)」、「Google Chrome(グーグル クローム)」などがあります。
つまり、厳密に言えばOSとは別のただのアプリケーションソフトだということです。IE以外にもブラウザは存在しており、これを、OSの機能として搭載するのはどうなの?ということです。
IEは、Windows95と同時期にMicrosotf社によって開発されました。Windows95の発売当時はオプション提供だったようですが、のちにWindowsに標準搭載されるようになります。
Windows 98の登場以降、インターネットが一般に広く普及し始め、これにより、他のブラウザ(Netscape Navigatorなど)との競争が激化しました。と言うよりも、IE以外のブラウザを知らないユーザーが大半で、他の選択肢を考慮しないという状況が生まれました。
そして、ブラウザにおけるIEのシェアは9割以上という状態になっていました。そのため、競合ブラウザが市場で競争できない状況となり、大きな議論を呼び起こしたのです。
法廷闘争の結果、最終的にMicrosoftがブラウザ選択画面を提供することを約束し、他のブラウザもインストール可能にすることで和解となったようです。
先述のとおり、現在でもWindowsにはブラウザ「Edge」が標準搭載されています。ただし当時と異なり、市場におけるEdgeのシェアは非常に低く、AppeやGoogleといった巨大な競争相手が存在するために大きな問題となっていません。
独占状態でない限り問題にはならないということですが、現代で言えば、OSのセキュリティ機能に対する議論があります。
昨今、サイバー攻撃が社会問題となり、セキュリティ対策が企業だけでなく個人でも重要になっています。悪意あるプログラムがインターネットを介してコンピュータに進入し、データと引き換えに身代金を要求する事例が相次いでおり、ランサムウェアという名前を聞いたことがあると思います。(セキュリティ対策についても、インターネットの仕組み の章で詳しく学習します)
Windowsには、「Microsoft Defender(ディフェンダー)」と呼ばれる総合的なセキュリティ対策ソフトが実装されています。セキュリティ対策ソフトとは、ウイルス対策をはじめとする総合的なセキュリティ対策を提供するアプリケーションソフトです。
これは、技術の進歩や社会的背景によるセキュリティニーズの高まり、他のOSの状況(他のOSも機能を実装した)などの理由によって、OSに統合されました。
理由はどうあれ、厳密にはOSとは別のただのアプリケーションソフトです。本来、こうしたアプリケーションがOSの機能として実装されると、IEと同じように問題提起される恐れがあります。(しかも無料です)
ただ、現在では多くの競合製品が存在し、ユーザーが選択できる自由があります。Microsoft Defenderは他の専用ソフトウェアと比べて遜色ないとされていますが、他社の専用ソフトウェアは、より高度な機能やサービスを提供しています。つまり、Microsoft Defenderだけで十分と考えるユーザーが少ないという状況があります。
また、他のセキュリティソフトをインストールした際には、自動的にMicrosoft Defenderが無効化される仕組みがあるため、競争が制限されないようになっています。
自由な競争が阻害されないように(していないと言えるように)提供の仕組みを考えたということですが、OSにどこまでの機能を持たせるべきかという議論は、様々な観点から今も続いています。
当然ながら議論の内容も技術の進化とともに変わり、今後もOSの機能についての意見は多様化していくと思われます。
抱き合わせ販売と市場公平性の確保
IEと同様に、かつて抱き合わせ販売について懸念されたソフトウェアがあります。
それは、Microsoft Office製品です。ご存じ、Word、Excel、PowerPointといったアプリケーションソフトです。これらについても、以前はWindowsの一部だと誤解されるケースがしばしばありました。
Windows 98が隆盛を誇った当時は、多くのパソコンメーカーや販売店がWindowsに標準搭載されている形で販売しており、WindowsとOfficeは「セット」として認識されやすい環境にありました。
また、Microsoftによるサポートや更新の方法も統合されていて、WindowsとOfficeが一体と感じられる一因となっていました。
こうして、Microsoft Office製品は瞬く間に普及し、WordやExcelが事実上の標準ソフトウェアになりました。その結果、多くの競合製品が市場から撤退もしくは衰退を余儀なくされたのです。
例えば、「一太郎」というアプリケーションソフトは日本国内で非常に人気があり、かつては標準的なワープロソフトでした。しかし、多くの企業や教育機関がWordを採用しために、一太郎も大きくシェアを落とすことになりました。
ただし、OfficeはIEのように完全に抱き合わせではなく、本来は別に購入するオプションであり、ユーザーはOfficeを購入するかしないかを選択できます。
現在では、Office製品に対する認識度も上がり、ユーザーはその他の代替アプリケーションを選ぶ自由があるため、法的な問題は特に発生していません。
Windowsはこの他にも、動画や音楽を再生する「Media Player(メディアプレーヤー)」や「映画&テレビ」、クラウド(インターネット)でファイルを保存・共有する「OneDrive(ワンドライブ)」、画像を表示・編集する「フォト」、文字情報だけを編集する「メモ帳」など、多くのアプリケーションを標準搭載しています。
これらは本来、数あるアプリケーションソフトのひとつにすぎないものです。それをOSのパッケージに追加して販売しているので、Windowsのシェアによっては、本来のOSの機能ではないアプリケーションソフトが独占・寡占状態になってしまうわけです。
これでは、他の企業はマイクロソフト社の顔色をうかがって商品開発するか、裁判を起こすしかありません。こうした事態は、ソフトウェアの健全な発展を阻害します。
しかし、今やWindows 98の時代はとうに終わり、Microsoft一強の時代ではなくなりました。
それぞれに競合する他社製品が活発で、逆にWindows関連製品は苦戦を強いられています。先述のとおり、こうした状況ではOSに機能を追加したところで問題にはなりません。
Microsoftは、IEの教訓からアプリケーションの提供方法の改善をすすめ、OSと抱き合わせのアプリケーションに対して、簡単に無効化したり、アンインストールできるようにしています。
こうした改善によって、ユーザーは不要なアプリケーションを取り除くことに抵抗がありません。抱き合わせで提供されることに対する抵抗感が軽減してきていると言えます。
ただ、パソコン初心者にとってはすべてがオールインワンで使えるほうがはるかに楽です。むしろ、そうしてほしいと思うことでしょう。しかし、こうした問題から、本来のOSの機能や役割を超えてアプリケーションソフトや機能を追加することは難しくなっています。
現在のように、OSと抱き合わせで提供したとしても、市場競争の自由を侵さない限り大きな問題になりませんが、ひとたび寡占・独占状態になると直ちに法的措置をとられるリスクがあります。
OSの本来の役割と機能について理解しておけば、OSに付属して提供されるアプリケーションや機能がどのようなものかを理解することができます。背景にあるこうした問題がどのように影響するのか、今後のOSの進化に期待しましょう。
更新履歴
- 2008年7月9日
- ページを公開。
- 2009年3月13日
- ページをXHTML1.0とCSS2.1で、Web標準化。レイアウト変更。
- 2018年1月24日
- ページをSSL化によりHTTPSに対応。
- 2024年10月31日
- 内容修正。
著者プロフィール
YAMANJO(やまんじょ)
- 経歴
- 岡山県出身、1980年生まれ(申年)の♂です。現在、総合病院で電子カルテなどの情報システム担当SEとして勤務。医療情報学が専門ですが、ネットワーク保守からプリンタの紙詰まり、救急車の運転手までこなしています。
- 医療情報技師、日本DMAT隊員。ITパスポート、シスアドなど、資格もろもろ。
- 趣味は近所の大衆居酒屋で飲むこと、作曲(ボカロP)、ダイビング。
- 関連リンク
- 詳細なプロフィールはこちら
- 作成したボカロ曲などはYoutubeへ
- X(Twitter)