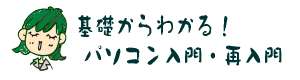- ホーム >
- 基礎知識 >
- インターネットの仕組み >
インターネットとは
限られたエリアの中で、限られた人のみが利用するネットワークがLANやWANでした。LAN、WANもインターネットも、パソコン同士またはネットワーク同士を相互に接続するという点では同じです。
しかし、LANやWANは限られた人しか利用することができない閉じたネットワークで、インターネットは誰でも利用できる開かれたネットワークです。
LANやWANには「管理者」がいて、そのネットワークの各種設定やユーザーの利用権限を決めたり、不正アクセスの監視などをしますが、インターネットにはそういった管理者は存在しません。(ルール策定のための公的な団体は存在します)
つまり、LANやWANでは管理者が、
通信ルールなどの各種設定を独自に設定することができる
ということになります。
前項で学習したイーサネットのように、いくつかの規格の中からそのネットワークに適したものを自由に選択することができます。その他にも様々な設定をネットワーク管理者が決めながらネットワークを構築していきます。
しかし、インターネットではそうはいきません。
インターネットは、全世界の無数のネットワークを相互に接続したとてつもなく巨大なネットワークだからです。WANも大きなネットワークですが、インターネットとは比較になりません。
そうしたインターネット内の無数のネットワークが、それぞれ自由な規格でネットワークを構築していたのでは、互いに通信することはできません。それではネットワークをつなぐ意味がなくなってしまいます。
そこで、
インターネットは接続するための共通ルールを設けている
のです。
例えば、通信の規格である「プロトコル」や、コンピュータ個別の識別番号である「IPアドレス」が決められていて、それに従わないとインターネットに接続することはできません。
つまり、インターネットでは、
通信ルールなどの各種設定を独自に設定することはできない
ということになります。
LANやWANではプロトコルやIPアドレスも自由に設定できますが、インターネットではインターネットのルールに従う必要があります。このインターネットの共通ルールは順を追って説明していきますので、まずは、インターネットが共通ルールのもとに成り立っているということを知っておきましょう。
もっとも、WANを構築するときでさえ、LAN同士の通信ルール(プロトコル)が異なったり、同じ識別番号(IPアドレス)が重なったりして通信できないことがあります。そのため、管理者はしっかりとしたルール作りが必要になります。
逆に、巨大なインターネットでは、もうすでにルールができあがっているのです。
つまり、LANやWANもインターネットのルールに従って構築すれば、インターネットと同じネットワーク形態となり、そのLANやWANをインターネットと接続することが可能になります。実際に、こうした形態がほとんどです。
そうなるとインターネットにLANやWANも含まれることになるのでしょうか?
答えは、NoでありYesでもあります。
ややこしいですが、明確に定義できるものではなく、見方によってNoともYesとも言えるのです。インターネットに接続されたLANやWANは、インターネットのルールに合わせたプロトコルやIPアドレスを設定しているので、WANの発展系がインターネットであるという考え方もできます。
しかし、WANが閉じたネットワークであることには変わりありません。なぜなら、インターネット側からLANやWANのネットワークを利用することはできないからです。
前項でも少し触れましたが、インターネットとLANとの境界に「ファイアウォール」という防御壁を設置して外部(インターネット側)からのアクセスを防止しているためです。
なぜかというと、インターネットの世界には残念ながら悪意を持ったユーザーも無数にいて、LANやWANに侵入して情報を盗み取ったり、コンピュータウィルスと呼ばれる悪意あるプログラムを作成してシステムを破壊したりといった犯罪行為をする者もいるからです。
LANやWANのネットワークをそんな悪者が利用しては困りますし、善意の第三者の利用であっても、機密情報などの見られては困る場合もあるでしょう。したがって、いくらLANやWANがインターネットとつながっていたとしても、閉じたネットワークであることに変わりありません。
一方、インターネットの概念は、どんなユーザーでも自由に利用できる開かれたネットワークであり、あらゆるデータがそのネットワークを流れていきます。そういった見方をすれば「No」と言えるかもしれません。
ところがここで「Yes」となるLANやWANがでてくるのです。
ネットワークを解放し、インターネットを流れるデータ通信の一部を担っている場合があるのです。こうなってくると、もうそのネットワークがインターネットの一部であることは間違いありません。
これはビジネスとして回線やネットワークの利用料を得ている場合であり、そうしたネットワークの集合体がインターネットであるという側面もあります。
インターネットのネットワークは国境をまたぎ、世界中に広がっています。日本からは海底ケーブルが何本も敷かれ、そこを通ってデータは海外とやり取りされます。
ケーブルを設置した業者や関係者がすべてボランティアでやっているわけではありませんし、様々な契約によってデータはいろいろなネットワークを利用させてもらいながら世界中を行き交っています。
このように、インターネットに含まれるLANやWANがあり、含まれないLANやWANがあると言い換えることができます。
そのため、インターネットが開かれたネットワークであることに変わりありませんが、開かれた閉じたという定義ですべて区別できるものではないのです。
インターネットは、
インフラストラクチャー(公共的な社会基盤)
になっているからです。
そう考えると、おぼろげながらインターネットの全体像が見えてくるのではないでしょうか。
見方によって違いを見出すことは可能ですが、そういった大きな視点に立つと、LANやWANもインターネットを構成する一部と言えます。国道と私道の違いはあっても、とちらも道路であることに変わりはないのです。
インターネットは管理者がいるわけではありません。参加する全員が意見を出し合ってつくり上げてきた国境も人種もない、人類ためのインフラなのです。
また、単にウェブサイトを見るためだけのものでもありません。ウェブはインターネットというインフラが生み出したサービスのうちのひとつになります。これまで、ウェブのみならずインターネットという巨大な社会基盤から様々なサービスが発明され発展してきました。
その他の具体的なサービスは次項以降で学習していきますが、ウェブの場合、ウェブサイトのファイルは、一般的にその企業のメインコンピュータやLANやWANの中に置いてあるわけではありません。
インターネット上に保存してそこにアクセスしてもらう
ことで情報やサービスを提供しています。
正確にはインターネット上のサーバコンピュータというウェブ配信専用の高性能コンピュータに保存しますが、インターネット上に保存したそのファイルの住所にあたるものが「アドレス」になります。アドレスは、URLまたはURIとも言います。一度は耳にしたことがあると思います。
また、インターネットでは、ファイルを1ヶ所にまとめて保管しておく必要がなく、インターネット上に分散して保存することができます。それらを結びつけるのが「ハイパーリンク」という技術になります。
ハイパーリンクは、URLを打ち込まなくても、クリックするだけで埋め込まれたURLに移動することができます。この分散処理の仕組みがインターネットでは大変重要です。
どこか1ヶ所にデータが集中してしまうと、その回線もしくはコンピュータがパンクしてしまうからです。そういった経緯の中からこの「リンク」の技術が生まれ、おかげでインターネットは拡大していくことになります。
そして、どんどん技術革新が起こり、今やインターネットはリアルタイムの決済や商取引には欠かせない社会基盤となり、あらゆる電子機器がインターネットとつながることを前提に開発されるまでになってきました。
では、そもそもインターネットに接続するにはどうしたらいいのでしょうか?
いくら世界中に広がっているといっても、勝手につながるわけではありません。スマートフォンなどでは自動的につながっているように錯覚しがちですが、インターネットに接続するには、
インターネット サービス プロバイダ(ISP)
と呼ばれるインターネット接続業者と契約し、一般回線からインターネットに接続してもらう必要があります。
インターネット サービス プロバイダ(ISP)は、単にプロバイダとも呼ばれます。(プロバイダはいくつも存在します)
家庭にはNTT等の回線事業者が引き込んだ電話回線や光ファイバー、またはケーブルテレビなどの通信手段があります。それを利用してインターネットに接続することができますが、単に回線があるだけでは接続することができません。
プロバイダに各種の設定を代行してもらってインターネットに接続できるようになるのです。(インターネット接続に必要なアドレス等を個人で取得することはまずできません)
スマートフォンなどのモバイル端末では、ソフトバンクやNTTドコモといった携帯電話会社が電波を利用してインターネット接続を代行しています。
ここまでは容易に理解できるはずですが、混同しがちなのは、プロバイダとNTT等の回線事業者を一緒にしてしまうことです。プロバイダはあくまで「接続代行業者」であり、NTT等の「回線事業者」とは異なります。
例えるなら、回線事業者が「高速道路」を運営する業者だとすると、プロバイダは「ETC」メーカーとなります。(ETCがなければ高速道路に乗れないとして)つまり、高速道路に乗るためにはプロバイダに設定をお願いするようになるわけです。
インターネット接続に必要な設定を「プロバイダ」から入手し、パソコンに設定する必要があります。(基本的には書類やハガキで届きます)そして、一般回線を利用してプロバイダに接続するので、NTT等の回線業者ともインターネット契約をしなければなりません。(詳しくは、インターネットへの接続(1) を参照してください)
ただし、プロバイダも独自の回線や光ケーブルなどのインフラ整備をすすめていますので、なかなか理解が難しいところです。
主要プロバイダは、バックボーンという専用回線を整備しています。これは、家庭からプロバイダまでの回線ではなく、プロバイダ同士の間で設置されたインターネットの通信を支える大容量の通信インフラです。
つまり、多くのデータが集中して流れるネットワークの基幹部分です。プロバイダ間といっても、国内、国外を問わず、またプロバイダ間に限定されているわけでもありません。
先述した海底ケーブルもそのひとつです。これらのバックボーンを利用することで我々ユーザーはインターネットを快適に利用することができるのです。そのため、プロバイダを選ぶ目安のひとつとしてバックボーンの信頼性をあげることもできます。
このように、インターネットは誰でも自由に利用できるネットワークでありながら、そのネットワークを利用するには、基本的に業者に接続してもらわなければなりません。
しかし、インターネットの世界に一歩足を踏み入れると無数の情報やサービスが溢れていて、様々な恩恵を受けることができます。
インターネットはどんな大規模なWANよりも大きく、世界中に広がっています。世界中の誰もが利用でき、また誰でも商品やサービス、情報を提供することができる夢のネットワークなのです。
インターネットの可能性は計り知れません。日進月歩で新しいサービスが誕生しています。その反面、法整備が追いつかなかったり、誹謗中傷などの負の面も進化しています。
インターネットにも危険やリスクが潜んでいます。予備知識を得たうえでインターネットを楽しんでください。
更新履歴
- 2008年7月25日
- ページを公開。
- 2009年4月24日
- ページをXHTML1.0とCSS2.1で、Web標準化。レイアウト変更。
- 2018年1月26日
- ページをSSL化によりHTTPSに対応。
- 2022年6月3日
- 内容修正。
参考文献・ウェブサイト
当ページの作成にあたり、以下の文献およびウェブサイトを参考にさせていただきました。
- 管理人のつぶやき
- Twitterのフォローお願いします!