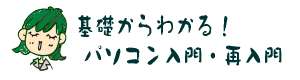コンピュータの5大装置(5大機能)
- 著者:YAMANJO
- 公開日:2008年7月25日
- 最終更新日:2025年1月9日
デバイスは外部デバイスと内部デバイスに区別することができました。本章では、コンピュータを構成する内部デバイスについて学習していきます。コンピュータの5大装置とは何か理解していきましょう。
コンピュータの5大装置とは
前章でデバイスについて学習しました。デスクトップパソコンをイメージすると、筐体(本体ケース)の外側と内側で、外部デバイスと内部デバイスに分けることができました。
外部デバイスは、主に筐体のインターフェース(USBなどの接続部分の規格)に接続して機能を追加するデバイスであり、その数は製品の数だけ無数に存在します。
対して内部デバイスは、筐体の内側でパソコンを構成する主要な装置が配置されている心臓部になります。そのため、内部デバイスにそれほど多くの種類はありません。
本章では、この内部デバイスについて学習していきます。コンピュータを構成する主要な装置とはどのようなもので、どのような役割があるのか理解していきましょう。
ただ、その前に「コンピュータ」と「パソコン」という用語の違いについて説明しておきます。
これまでも同義語のように使ってきましたが、厳密に言うと、パソコンは「パーソナルコンピュータ」の略で、数あるコンピュータの種類のひとつです。したがって、コンピュータと言えば、パソコンを含むすべてのコンピュータを意味します。
本項で学習する装置はパソコンのみならず、基本的にすべてのコンピュータに共通する概念になります。そのため、パソコンとコンピュータを使い分けることがありますが、大きな違いはありません。(詳しくは、コンピュータの種類 で学習します)
では、話を戻します。
コンピュータを構成する装置は、
コンピュータの5大装置(5大機能)
と呼ばれています。
そのまんまと言えばそのとおりですが、必ずこの5つの装置・機能によってコンピュータが構成されています。逆に言えば、どれかひとつでも欠けるとコンピュータとは言えません。
それぞれの詳細は次項から詳しく学習しますので、本項では概要のみに留めますが、重要なのは、どのような装置からコンピュータが成り立っているのかを理解しておくことです。
また、内部デバイスがこの5つの装置だけというわけではありません。あくまで、コンピュータを構成する必要不可欠な装置が5つという意味なので、注意してください。
入力装置
コンピュータに命令を与えるための装置です。人間が命令を入力するための装置になります。
この装置がなければ、コンピュータを操作することができません。パソコンで言えば、マウスやキーボード、スマートフォンでは、タッチスクリーンなどの装置になります。
また、マイクやカメラといった装置も場合によっては入力装置になり得ます。
出力装置
入力装置によって命令された処理の結果を、人間に理解できるかたちで出力するための装置です。
簡単に言えば、画面に表示したり、紙に印刷したりすることです。具体的には、プリンタやモニタ(ディスプレイ)、スピーカーなどの装置になります。
記憶装置
命令の処理に関する一時的な情報や、プログラムファイルやデータファイルを保存するための装置です。
主記憶装置と補助記憶装置に大分されます。主記憶装置はメモリ、補助記憶装置はストレージと呼ばれています。メモリにはRAMやROM、ストレージにはSSDやHDDなどがあります。
演算装置
コンピュータの頭脳にあたる装置で、2進数の処理(計算)を行います。四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)や大小比較など、さまざまな計算を行います。
2進数の処理では、加法(足し算)のみで、四則演算すべてを行うことができます。そのため、加法を基本として専用の回路を用いることで四則演算を超高速行っています。
演算装置は、CPUという装置の演算ユニット部分が該当します。
制御装置
これらの各装置に命令の実行に必要な信号を送り、システム全体を制御するための装置です。入力装置、出力装置、記憶装置、演算装置の制御を行う装置です。
例えば、入力装置から「印刷」という命令が下された場合、制御装置はその命令を解釈し、印刷に必要な一連の動作を記憶装置(メモリ)や、出力装置(プリンタ)などの各装置に指示・調整します。
制御装置は、CPUという装置の制御ユニット部分が該当します。
デバイスの制御はOSの主な役割のひとつと学習してきましたが、OSはCPUを通じてデバイスを間接的に制御します。具体的には、OSがデバイスドライバを利用して制御命令をCPUに渡し、CPUがそれをもとに物理的な制御を行っています。
以上、入力装置・出力装置・記憶装置・演算装置・制御装置の5つがコンピュータの5大装置になります。
言葉からは難しそうな印象を受けますが、それほど難解ではありません。よく例に出されるのが、人間の各器官にあてはめてみるイメージです。
入力装置は、外部からの情報を取り入れる機能を持つ「目」や「耳」に相当し、出力装置は、考えた結果を形にするための機能をもつ「手」や「口」になります。
記憶装置は、記憶する機能をもつ「脳の記憶部分」、演算装置・制御装置も「脳の演算部分・制御部分」になります。(ほとんど脳になってしまいますが)
次項から、各装置についてそれぞれ詳しく学習していきます。
更新履歴
- 2008年7月25日
- ページを公開。
- 2009年4月6日
- ページをXHTML1.0とCSS2.1で、Web標準化。レイアウト変更。
- 2018年1月25日
- ページをSSL化によりHTTPSに対応。
- 2025年1月9日
- 内容修正。
著者プロフィール
YAMANJO(やまんじょ)
- 経歴
- 岡山県出身、1980年生まれ(申年)の♂です。現在、総合病院で電子カルテなどの情報システム担当SEとして勤務。医療情報学が専門ですが、ネットワーク保守からプリンタの紙詰まり、救急車の運転手までこなしています。
- 医療情報技師、日本DMAT隊員。ITパスポート、シスアドなど、資格もろもろ。
- 趣味は近所の大衆居酒屋で飲むこと、作曲(ボカロP)、ダイビング。
- 関連リンク
- 詳細なプロフィールはこちら
- 作成したボカロ曲などはYoutubeへ
- X(Twitter)